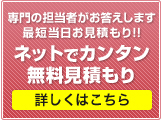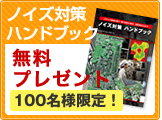■EMC対策の部品の選択(抵抗編)
受動部品は寄生的な抵抗、容量、そしてインダクタンスを含んでいる。
EMC問題が発生する高周波領域では、これらの寄生成分が問題となり、その部品が異なった挙動を示す。
例えば、 高周波領域においては、
皮膜抵抗はコンデンサ (0.2pF 程度の並列容量により) になるか、
あるいはインダクタ (リード・インダクタンスと抵抗により) となる。
また、これら2つが共振し、より複雑な挙動を示すこともある。
1kΩ 以下の皮膜抵抗は通常は数百 MHz まで抵抗性を持つが、巻線抵抗は数 kHz 以上では使いものにならない。
これらの、寄生成分が小さく、より高い周波数までその抵抗性を持つ為、
EMC対策としてSMD抵抗が推奨される。
例えば、1kΩ以下のSMD抵抗は、通常は 1GHz でも抵抗性を持つ事が出来る。
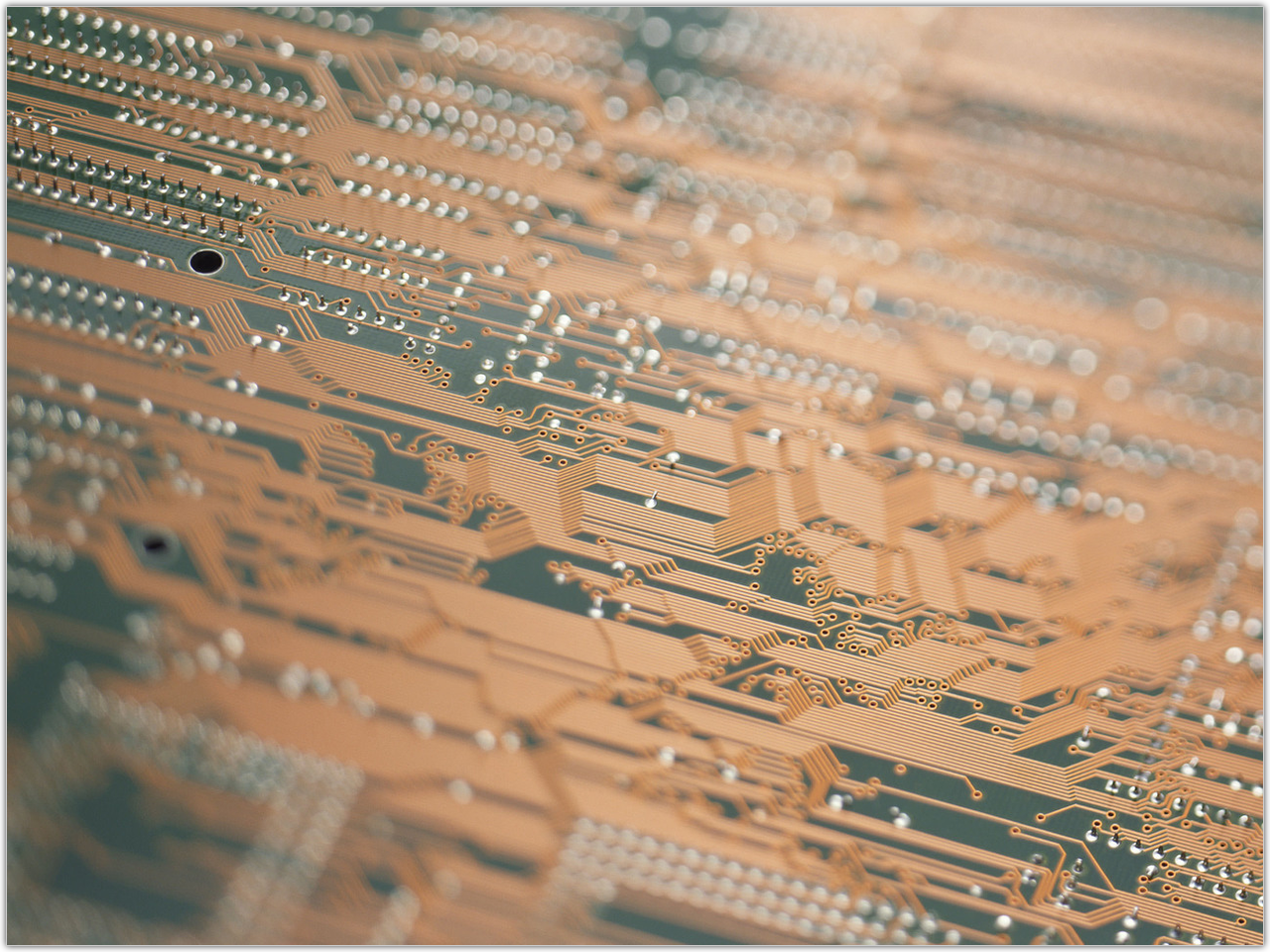
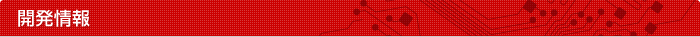
- TTL とCMOS 回路のインタフェース
- マイコンやFPGAでI/O電圧が3.3V時の注意点
- マイコン、FPGA、インターフェースIC等で,I/O電圧が異なる時の対処法①
- マイコン、FPGA、インターフェースIC等で、I/O電圧が異なる時の対処法②
- EMC のためのコンポーネントの選択
- EMC対策の部品の選択(抵抗編)
- EMC対策の部品の選択(コンデンサ編)
- EMC対策のデジタル回路の設計(1)
- EMC対策のデジタル回路の設計(2)
- 「SI」、「PI」とは
- スイッチング電源によるノイズ問題
- 電子部品で取扱う波形の性質
- LVDSについて
- デジタルICの電源ノイズとデカップリング回路の必要性(1)
- デジタルICの電源ノイズとデカップリング回路の必要性(2)
- デジタルICの電源ノイズとデカップリング回路の必要性(3)
- デジタルICの電源ノイズとデカップリング回路の必要性(4)
- 分布定数回路の必要性
- 伝送ラインの等価回路(l<<λ)
- sin波形
- 終端処理
- プロービングとテストピン
- 回路設計者と難燃性
- 基板レイアウトと熱
- 様々なインターフェースを使いこなすには
- バス・インターフェースの選び方
- 汎用深堀① チップ抵抗 前編
- 汎用深堀② チップ抵抗 後編