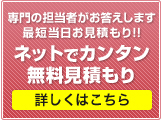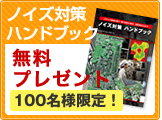デジタルICの電源ノイズとデカップリング回路の必要性 (4) | パターン設計開発支援サイト
コンデンサだけで、高い周波数まで、広げようとすると別の問題が発生します。
それは、コンデンサの容量が周波数によって変わってしまう事と
共振点を越えた周波数帯域ではインダクタンス成分が現れてくる事です。
これによって、持っている自己の残留インダクタンス成分によって
L,C 共振が起こってしまうためです。
これを、防止する為に、コンデンサ間にフェライトビーズなどを入れる、
容量の間隔を10倍以内とする等の手法が有ります。
フェライトビーズは、挿入損失向上には有効なのですが、
インピーダンスを下げる効果は小さくなります。
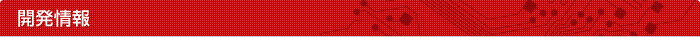
- TTL とCMOS 回路のインタフェース
- マイコンやFPGAでI/O電圧が3.3V時の注意点
- マイコン、FPGA、インターフェースIC等で,I/O電圧が異なる時の対処法①
- マイコン、FPGA、インターフェースIC等で、I/O電圧が異なる時の対処法②
- EMC のためのコンポーネントの選択
- EMC対策の部品の選択(抵抗編)
- EMC対策の部品の選択(コンデンサ編)
- EMC対策のデジタル回路の設計(1)
- EMC対策のデジタル回路の設計(2)
- 「SI」、「PI」とは
- スイッチング電源によるノイズ問題
- 電子部品で取扱う波形の性質
- LVDSについて
- デジタルICの電源ノイズとデカップリング回路の必要性(1)
- デジタルICの電源ノイズとデカップリング回路の必要性(2)
- デジタルICの電源ノイズとデカップリング回路の必要性(3)
- デジタルICの電源ノイズとデカップリング回路の必要性(4)
- 分布定数回路の必要性
- 伝送ラインの等価回路(l<<λ)
- sin波形
- 終端処理
- プロービングとテストピン
- 回路設計者と難燃性
- 基板レイアウトと熱
- 様々なインターフェースを使いこなすには
- バス・インターフェースの選び方
- 汎用深堀① チップ抵抗 前編
- 汎用深堀② チップ抵抗 後編