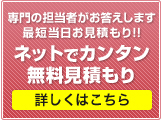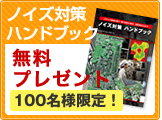回路設計者と難燃性 | パターン設計開発支援サイト
難燃性に関心の無い回路設計者の方も多い思いますが、
実は難燃性と回路設計は深い関わりがあります。
難燃性と言うと、基板のマーキング”UL94V-0”を
連想する方も多いと思います。
UL94V-0が何をしめしているかと言うと、
ULの定める個体プラスチック材料の燃焼性試験UL94V-0を
パスしたことを示しています。
個体プラスチック材料とは、
FR-4の基板の場合ガラス・エポキシを指しています。
ここまで読むとやっぱり樹脂=化学の話じゃないかとなりますが、
続きがあります。
見えないエネルギーである電気は、
当然ながら帯電や漏電があっても見えません。
この部分にうっかり触れると火花が散る危険があります。
この点から電気回路は難燃性が問われます。
燃焼性試験は数段階のグレード分けがあります。
(良く燃える→燃え難い)
固体プラスチック材料
UL94HB → UL94V−2 → UL94V−1 → UL94V−0 → UL945VB → UL945VA
薄手プラスチック材料 UL94VTM−2 → UL94VTM−1 → UL94VTM−0
発泡材料 UL94HBF → UL94HF−2 → UL94HF−1
電気回路に応じてこのグレードの使い分けが必要になります。
最後にコネクタ等で良く使われるナイロン66と言われる樹脂があります。
ナイロンより難燃性に優れており、
UL94V-2からUL94V-0まであります。
UL94V-1以上の難燃性を求める場合は注意が必要です。
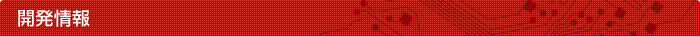
- TTL とCMOS 回路のインタフェース
- マイコンやFPGAでI/O電圧が3.3V時の注意点
- マイコン、FPGA、インターフェースIC等で,I/O電圧が異なる時の対処法①
- マイコン、FPGA、インターフェースIC等で、I/O電圧が異なる時の対処法②
- EMC のためのコンポーネントの選択
- EMC対策の部品の選択(抵抗編)
- EMC対策の部品の選択(コンデンサ編)
- EMC対策のデジタル回路の設計(1)
- EMC対策のデジタル回路の設計(2)
- 「SI」、「PI」とは
- スイッチング電源によるノイズ問題
- 電子部品で取扱う波形の性質
- LVDSについて
- デジタルICの電源ノイズとデカップリング回路の必要性(1)
- デジタルICの電源ノイズとデカップリング回路の必要性(2)
- デジタルICの電源ノイズとデカップリング回路の必要性(3)
- デジタルICの電源ノイズとデカップリング回路の必要性(4)
- 分布定数回路の必要性
- 伝送ラインの等価回路(l<<λ)
- sin波形
- 終端処理
- プロービングとテストピン
- 回路設計者と難燃性
- 基板レイアウトと熱
- 様々なインターフェースを使いこなすには
- バス・インターフェースの選び方
- 汎用深堀① チップ抵抗 前編
- 汎用深堀② チップ抵抗 後編